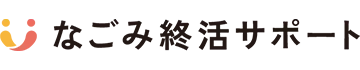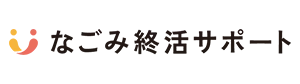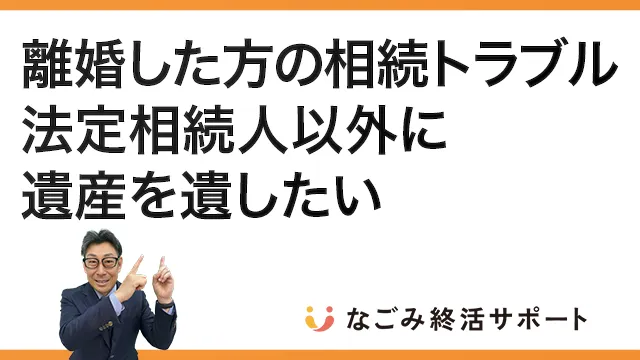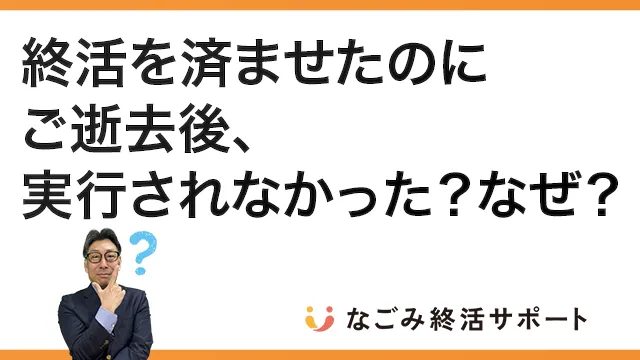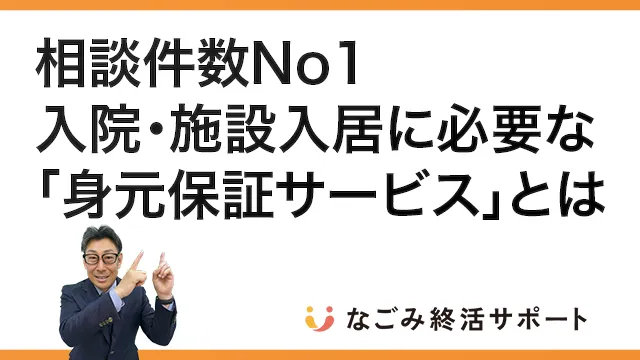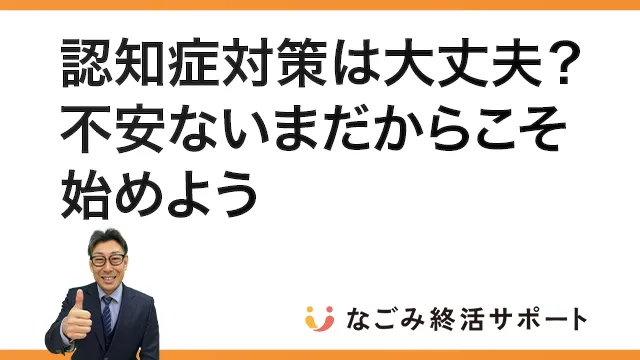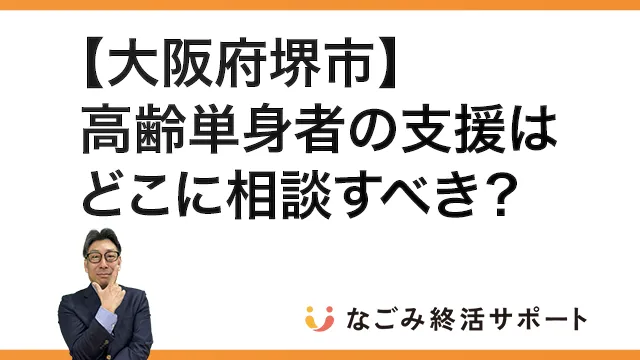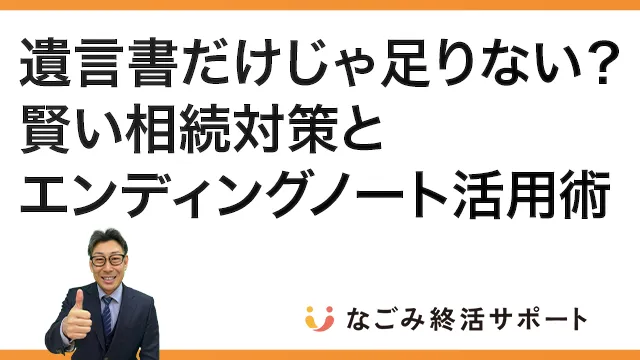認知症対策は大丈夫?不安ないまだからこそ始めよう
いまは大丈夫。でも、将来の自分に備えていますか?
「まだ大丈夫」「うちは家族に認知症の人はいないから」と思っていませんか?
確かに、認知症は誰もがすぐに直面するわけではありません。しかし、誰にでも起こりうる“身近な将来”のリスクであることを忘れてはなりません。
2023年の厚生労働省の推計によると、日本における65歳以上の認知症の人の数は約600万人、高齢者の7人に1人が該当するとされています。さらに、2025年には730万人を超えると予測されています(※厚生労働省『認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)』)。
年齢を重ねれば誰にでも起こり得る脳の変化。それが、日常生活に影響を及ぼす形で現れるのが「認知症」です。そうなる前に、自分自身と家族を守る備えができているでしょうか?
認知症のサインは「ある日突然」ではない
認知症はある日突然やってくると思われがちですが、実際には「発症前の段階(軽度認知障害/MCI)」が数年にわたって続くことが多いといわれています。この段階で気づき、生活習慣や環境を整えることで進行を遅らせたり、予防につなげたりすることも可能です。
たとえば次のような小さな変化が見られた場合、それは注意のサインかもしれません。
・今まで使いこなしていたスマホや家電が急に使えなくなる
・同じ話を短時間で何度も繰り返す
・財布や鍵の置き忘れが増える
・運転中に道に迷うことが増えた
・怒りっぽくなる、急に無気力になる
これらは老化による単なる物忘れと区別がつきにくいこともありますが、「生活に支障をきたしているかどうか」が判断のポイントです。
できることは意外とたくさんある
認知症対策は、医療だけに頼るものではありません。予防・早期発見・進行抑制の三本柱で考えることが大切です。
■日常生活の工夫
運動習慣:週3回以上のウォーキングや軽運動は、脳の血流を促し、認知症リスクを下げることが報告されています。
食事の見直し:地中海式食事法(野菜・魚・オリーブオイル中心)や、減塩・減糖の意識も大切。
知的刺激:読書・書き物・人との会話・パズルや囲碁・麻雀など、脳を使う活動が推奨されています。
社会参加:地域の活動に参加したり、趣味のサークルに加わることは孤立の予防につながります。
■医学的対策
定期的な認知機能チェック:年1回の認知症スクリーニング検査を受ける習慣も有効です。
かかりつけ医との連携:かかりつけ医がいれば、初期症状への対応もスムーズです。
「備える人」が、自分と周りを守る
認知症は避けられない運命ではありません。早めに生活を整え、小さな変化に気づく力を育てることこそが、未来の自分への最大のプレゼントです。
不安がない「いま」だからこそ、冷静に情報を集め、準備を始める好機です。
何歳であっても、遅すぎることはありません。
あなたの「これから」を守るために、今日からできる一歩を踏み出してみましょう。